カテゴリーを選択
トップ > 特集 特別対談「"変革"に挑む」森川博之さん×足立正親 > P3
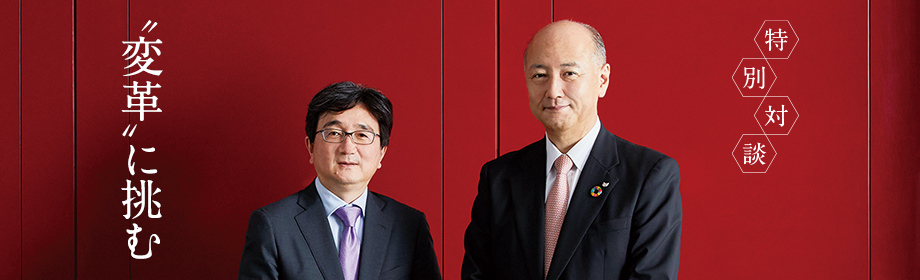
デジタル時代に対応した企業変革、すなわち「デジタルトランスフォーメーション(DX)」は、いまやビジネスシーンの合言葉となった。デジタル技術が社会にもたらす新たな可能性とはどういったものなのか。第一線で研究してきた東京大学の森川博之教授は、DXにおいてテクノロジーはあくまで「手段」にすぎず、そこから新しい価値を生み出すのは「人」だと語る。今、DXを実現するために求められるマインドセットや、組織の在り方とは?
その核心を、キヤノンマーケティングジャパン 代表取締役社長の足立正親と語り合った。
森川
組織づくりの話でいうと、DXと「CX(コーポレートトランスフォーメーション)」は両輪であるべきだと私は考えています。
つまり、DXをやるからには、会社の制度や仕組みそのものに手を付けなくてはなりません。例えば、ITツールを活用しテレワークができるようになったことで、移動の時間やコストが削減でき、業務の効率化が進んだというのが分かりやすい成果ですが、これが進むと「働き方をどうするのか」「評価はどうあるべきか」といった簡単ではない問題が浮上します。そこに向き合わないことには、DXは「本物」にはならないと思うのです。
足立
弊社もテレワークを導入していますが、移動時間の削減だけでなく、生産性を高め新たな価値を生み出す真のDXに結び付けるためには、やるべきことが残っています。失敗を恐れず挑戦することも評価するような制度への再設計も含め、カルチャーそのものを変えないことには定着しないだろうと痛感しています。
森川
むしろ、そちらが本筋です。人が介在する分、企業カルチャーはそう簡単には変わりません。電気が発明されたときも、街灯や家庭の灯りが電気に変わるのはあっという間でしたが、「工場」に電気が入るまでには数十年かかっています。というのも、蒸気機関で動いていた工場を電気に変えようとすると、職員の仕事のやり方から賃金体系までがガラリと変わってしまうからです。
テクノロジーを導入すれば勝手に変革が成されるわけではありません。本物のDXには10年、20年スパンの年月がかかることを前提に、トライアンドエラーを繰り返していくことが、結果的には最短コースになるのではないでしょうか。
足立
一企業が変えられることには限りがありますから、パートナー企業と力を合わせて協働することも必須でしょうね。
森川
おっしゃる通りです。私はかねてより、大企業と中小企業のコラボレーションによってDXは加速すると考えています。グローバルなインフラやブランド力といった大企業のケイパビリティ(組織的な能力や強み)をうまく使い、スタートアップのリソースと組み合わせれば、最も効果的なイノベーションが生まれるでしょう。
その際、イメージしているのは、ゲームの『テトリス』です。さまざまな形状のピースを、クルクル回転させながら、しかるべき位置にスポッと入れる。人にも企業にもそれぞれ得意不得意があるので、各々にふさわしい役目を割り当てることが重要になってきます。
足立
その「ピースを回転させて、動かす」人こそが、DXの要ということになりますね。
森川
その役割を担うのが、冒頭でお話しした「仲介者」です。私は「カタリスト(触媒)」と呼んでいます。この役割にはやはり、技術系よりも営業を経験してきた人の方が向いているでしょう。
また、カタリストに限らず、DXに関わる全ての人には「きれいな心」をあらためて持ってほしいと思います。今後ますます、異業種間連携をする機会は増えるでしょう。そこで成功に導くには、お互いの価値観を尊重し、敬いながら共にWin-Winの関係を築くことが重要なのではないでしょうか。
足立
それはまさに、お客さまとの共創により事業を通じて社会課題の解決に取り組んでいくという、弊社グループが取り組んでいるサステナビリティ経営そのものであり、わが意を得たりという思いです。本日はありがとうございました。

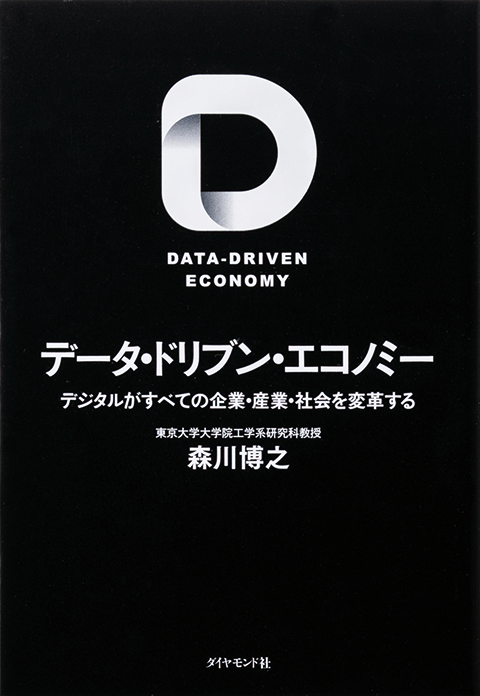
今やDX(デジタルトランスフォーメーション)はビジネス用語としてすっかり定着しつつある。DXの本質はデータの活用にあるともいわれ、21世紀の石油とされるほどデータは価値ある資源。本書はその意味を解説すると同時に、データにどう向き合うべきかを教えてくれる。「データ・ドリブン・エコノミー」とは、リアルな世界から集めたデータが新たな価値を生み出し、あらゆる企業・産業・社会を変革していく一連の経済活動だと定義する。
著者は、インターネットが普及し始めてから約20年間のデジタル革命は、ネット上の「ウェブデータ」が主役だったと指摘する。閲覧履歴・購買履歴、SNSの個人関連データなどが「情報爆発」をもたらし、これらを集めたGAFAのようなプラットフォーマーが競争優位に立っていた。
しかし、今後は「リアルデータ」が主役になると著者は予測する。仕事や生活の中にはデジタル化されていない膨大な物的資産があり、経験と勘に頼って行われてきたアナログプロセスがある。こうしたリアルな世界からデータを集める動きが今、活発になりつつある。本書は、製造やサービス、医療・ヘルスケア、農業など幅広い分野の国内外の事例を紹介している。
例えば、コマツは早くから建設機械にセンサーを取り付け、位置や稼働時間、燃料の残量、二酸化炭素の排出量などのデータをリアルタイムで取得し、サービスビジネスにつなげてきた。さらに、工事現場の3次元データを組み合わせることで、工事の自動化にも取り組んでいる。著者は、リアルデータの活用は地味で泥臭い領域であり、実は日本企業や日本人が得意な分野であるとも語っている。
では、リアルデータを活用してDXを推進するにはどうすれば良いのか。多くのプロジェクトがAIやIoTで集めたリアルデータを活用しようとしたが、結局PoC(概念実証)で終わってしまい、「PoC疲れ」という言葉も聞く。著者はその理由を、何のためにAIやIoTを導入するのかをしっかりと考えず、デジタル化自体が目的になってしまうことが大きいと分析する。
AIもIoTも単なるツールであり、データによって新しい価値を生み出すという意識が重要である。今すぐDX実践のポイントを知りたければ、最終章から読み始めるのも良いだろう。
(評・日経BP総合研究所 フェロー 桔梗原 富夫)