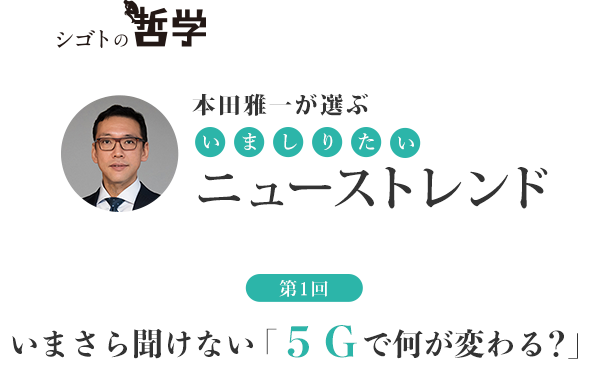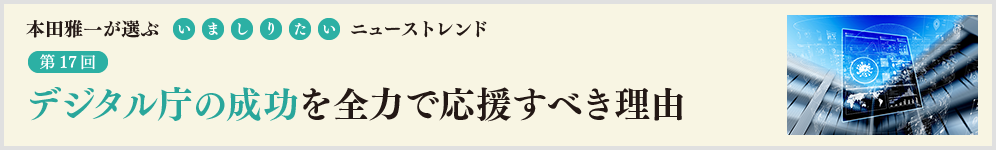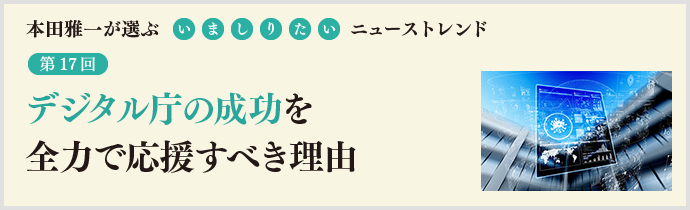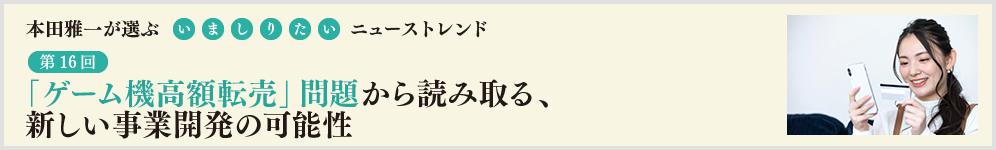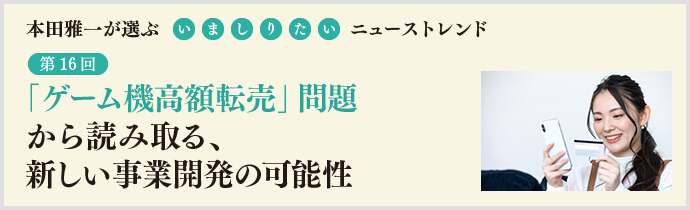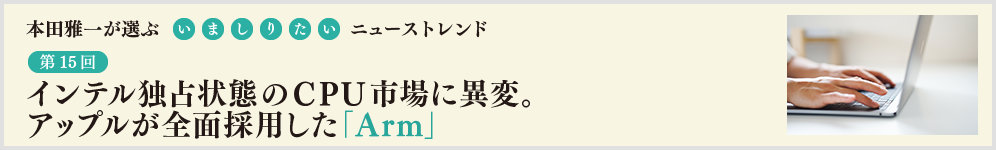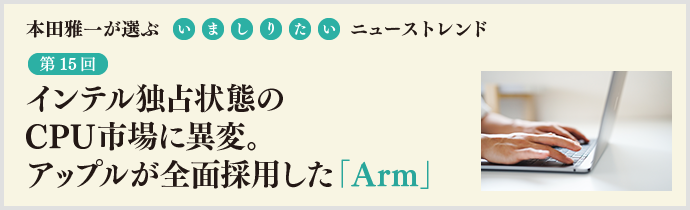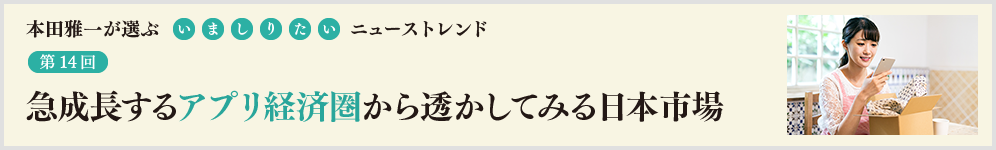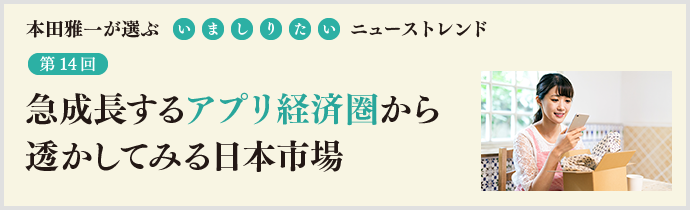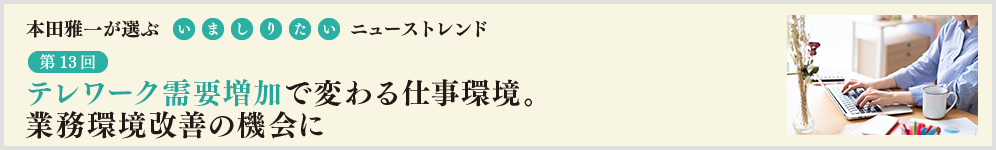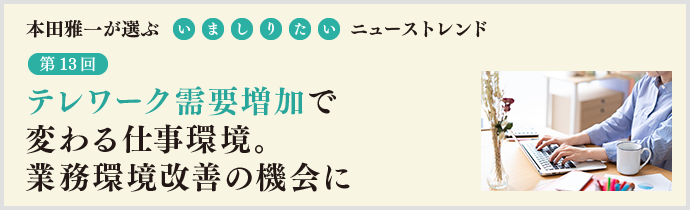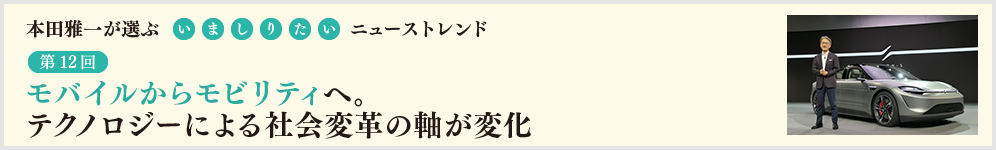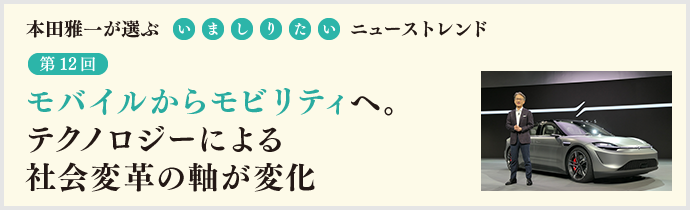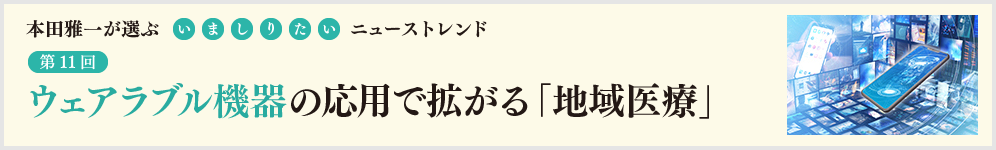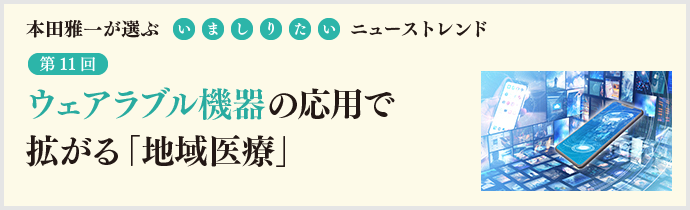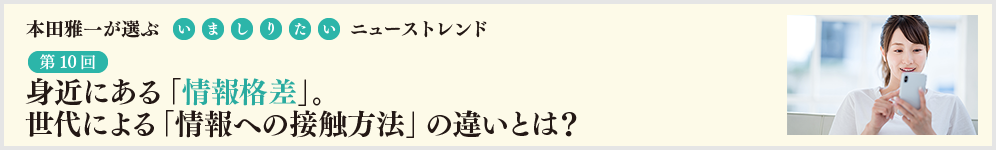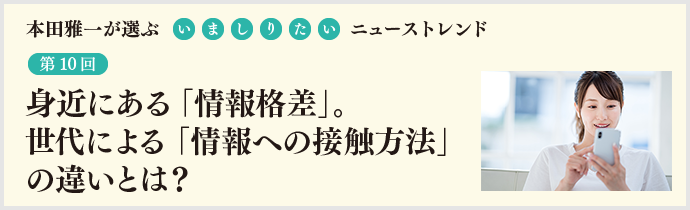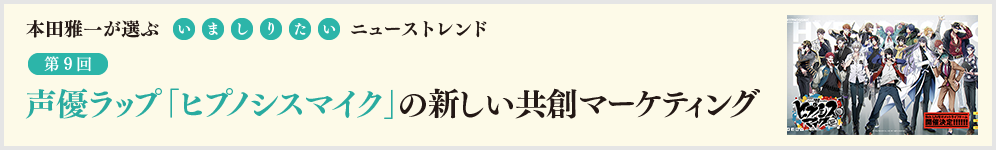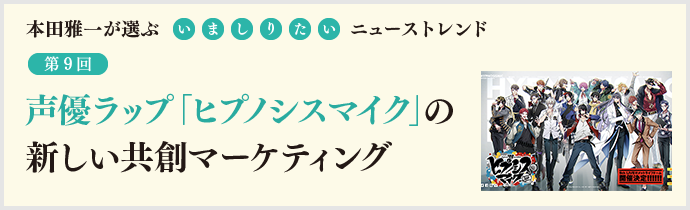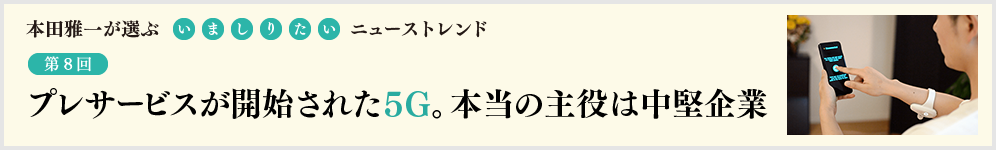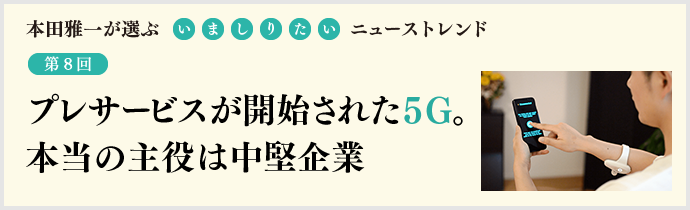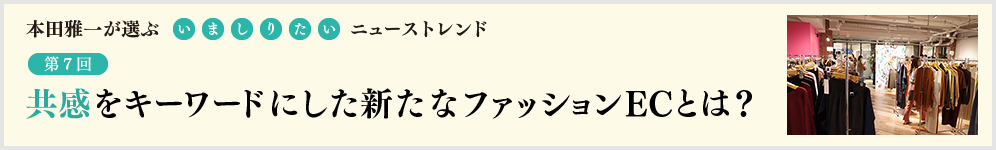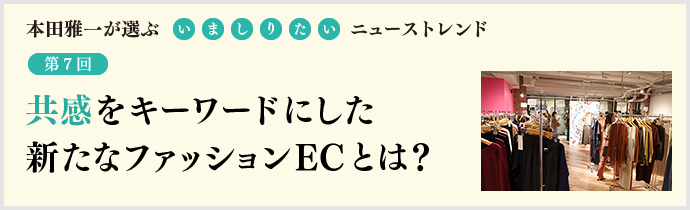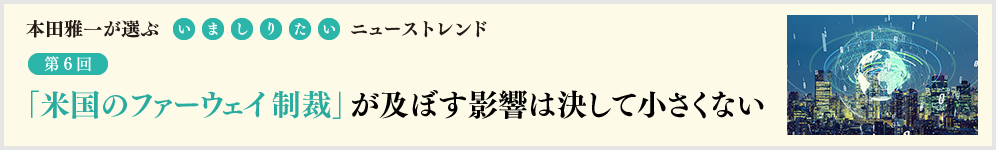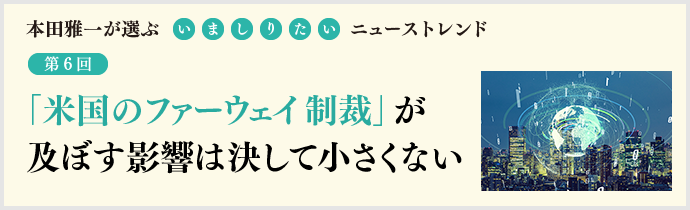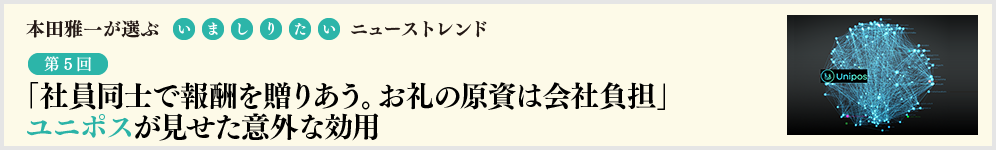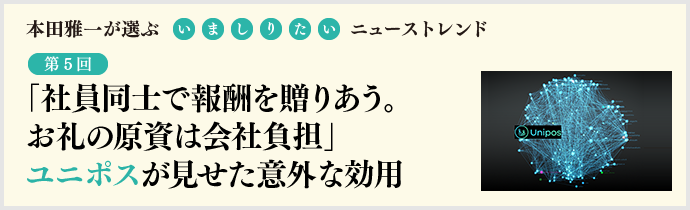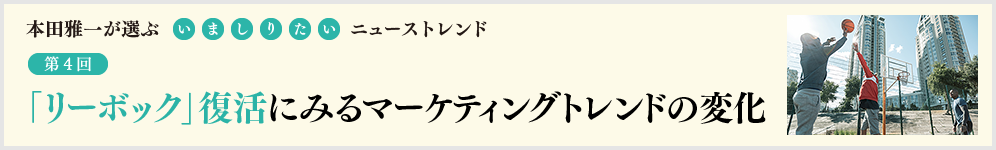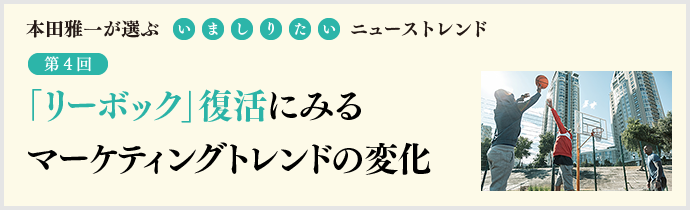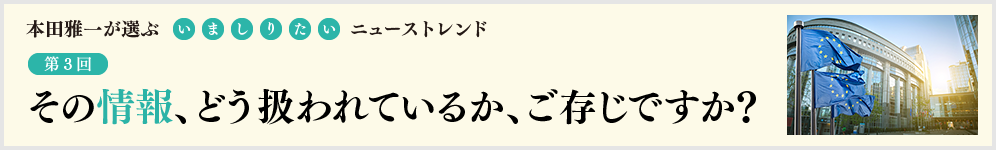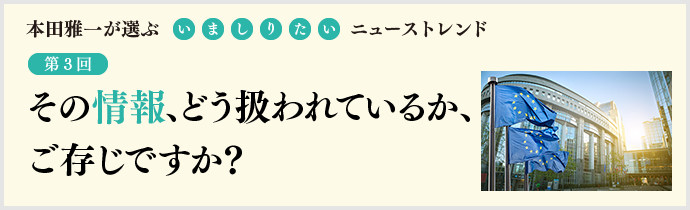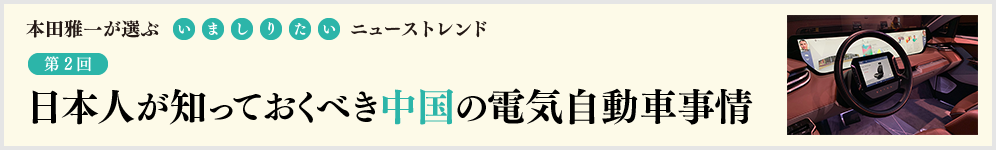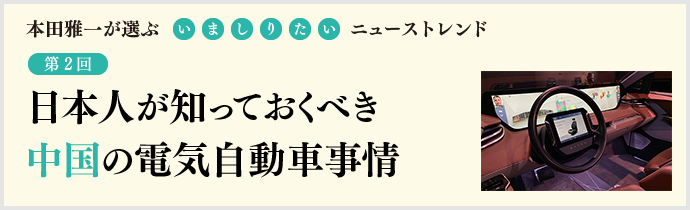近年、通信だけではなく、自動車や街づくり、あるいはスタジアムを中心とした複合商業施設の建設など、さまざまな分野で登場する「5G」というキーワード。ほとんどの方が、第五世代移動通信システムのこと(5G = 5th Generation Mobile Network)だとご存知でしょう。
移動通信システムはおよそ10年単位で技術の世代が更新されてきました。日本の場合、3Gは2001年から、4Gは2011年から運用が開始されています。そして2020年、いよいよ5Gへの移行が始まります。
「つまり、通信速度が速くなるから、もっと便利にスマホが使えるってことですね?」
これまでの経験則からすれば、確かにそのとおり。3Gへの移行では様々なアプリやゲーム、音楽といったコンテンツの流通が活性化しましたし、4Gではさらに進んで動画や音楽のストリーム視聴など、固定通信回線に近い使われ方がされるようになってきました。

通信速度が速くなると、それまではデータ転送の時間や通信コストなどの制約から無視されてきた使い方が、どんどんされるようになっていき、やがて常識を変えていきます。
5Gでも通信速度は速くなるのですが、実は注目されている理由は、単純に高速になるということだけではありません。社会全体を変えてしまう力、これまで携帯電話網とは無関係と思われていた事業領域にも革命を起こし、商品、サービス、コンテンツ、設備・施設、あるいは交通網や物流を含む社会全体に変化をもたらすからこそ注目され、また多様な分野のニュースになっているのです。
知っておきたい5G、
4つの特徴
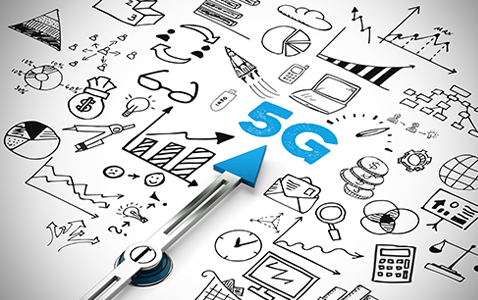
5Gの特徴は大きく分けると3つあると言われています。「高速」「大容量」「低遅延」の3つですが、ここにもう1つ「低消費電力」も加えた方が、その特徴を見通しやすいでしょう。
速度は4Gが最大1Gbpsなのに対し、5Gは最大10Gbpsを目指して進化させ、より大きなデータの転送、あるいは同時に多くの人が大量のデータ通信を行う場合に対応できるようになりますが、5Gで社会が変化する理由はそれ以外の特徴にあります。
まず、大容量。あらゆるモノがネットへとつながることで、その価値や使われ方が変化するIoT(Internet of Things)ムーブメントが広がってきましたが、5Gでは社会全体あらゆるモノが移動通信システムにつながることを想定しています。
しかし、ここで問題になるのが同時に接続できる端末の数。スマートフォンなどの端末を想定していた従来のシステムでは、基地局あたり1000程度までしか同時接続できず、全国規模でも1億端末程度。これではあらゆるモノがつながる時代には対応できません。
そこで5Gはこの数(システム容量)を1000倍(基地局あたり100万接続)にまで引き上げることを目標に設計されており、基地局が同時に通信できる機器の数も100倍になります。
次に、低遅延。データを送出してからもう一方の端末に届くまでの時間は1/10(1ミリ秒)にまで短縮されます。これにより様々な移動体が通信網によって、クラウド型サービスなどから制御可能になります。
例えば自動運転車は自律的に自動航行する能力を内包していますが、そこに5Gで接続されたサービスが加わることで、より安全に、また社会全体を見渡した効率的な交通網が構築できます。ドローンや無人配送車などによる物流革命も、5Gの低遅延という特徴が効いてきますし、ロボットを活用した農地管理などの応用も広がるでしょう。
そして、意外に大きな意味を持つのが低消費電力です。5Gは高速大容量の通信システムですが、そのフルスピードを使うのではなく高効率な通信を活用し、低消費電力で常時通信網に接続される小型デバイスにも応用できる適応幅の広さもあります。これまでであればBluetooth Low Energy(BLE)などの手法で、スマホを通じて接続していたような機器が、今後はどんどん5Gへと直接つながっていくでしょう。
しかし、これらは技術的な特徴であって、5Gによる社会変革を支える要素でしかありません。本当の変化は、想像を超えた先にあります。
「5G社会」をつくるのは、
すべての業種のひとたち

社会全体がネットワークで接続される。すなわち、端末を開発する通信機器メーカーや、それらと連携したサービスをつくる携帯電話事業者、コンテンツプロバイダーだけではなく、あらゆる業種で使われる“モノ”がネットワーク化され、サービスとともに運用されることになります。そうなったとき、どのような新しい事業領域が生まれるのか。今はまだ想像の中の世界でしかありません。
地方に住むお年寄りへの医療サポート、自動運転化による車内エンターテインメントの充実、お店の自動会計・チェックアウト、ドローンを使った農薬散布や物流など、5G社会がどうなっていくのかを説明する動画もありますが、それだけにとどまることはないでしょう。
総務省は2018年10月に「5G利活用アイデアコンテスト(https://5g-contest.jp)」の実施を発表しました。5G利活用の実験は、すでにいくつもの企業が共同で行ってきましたが、今回は個人も対象にしていることが大きな特徴。アイデアさえあれば、年齢、所属、経験などは一切問われません。もちろん、地方自治体や各種団体、大学なども参加できます。
政府の取り組みとしては前例のないものですが、こうしたコンテストが行われる背景には“想像を超えた先”に5Gの可能性が広がっているからにほかなりません。「自分たちの仕事はネットや通信とは無関係」と思わず、まるでSF小説のアイデアを考えるかのように、足元の仕事、事業の未来を想像してはいかがでしょう?
そこには新しい可能性が見つかるかもしれません。

本田 雅一(ほんだ まさかず)
フリージャーナリスト・コラムニスト
テクノロジジャーナリスト、オーディオ&ビジュアル評論家、商品企画・開発コンサルタント。
技術を起点に経済的、社会的に変化していく様子に着目し、書籍、トレンドレポート、評論、コラムなどを執筆。