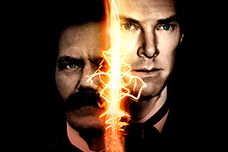これからは「モビリティの時代だ」。
ソニー社長兼CEO吉田憲一郎氏は、1月に米ラスベガスで開催されたCESの会場でそう断言しました。過去10数年に渡る「モバイルによる社会変革の時代」が終わり、これからは「モビリティによる社会変革が始まる」というのです。
CESと言えば、その元をただせば全米家電協会、すなわちConsumer Electronics Associationが主催するトレードショーでしたが、現在のCESは様変わりしています。既存企業の事業モデルを一から見直して再構築する「デジタル・トランスフォーメーション(DX)」事業が近年盛り上がり、IT企業の収益を支えているが、CESはまさにテクノロジーで社会変革をもたらす「DX展示会」になってきたのです。
そのCESでもっとも大きなテーマだったのが、「モビリティによる社会変革」でした。
エレクトロニクス業界は
モバイルからモビリティへ

CESではソニーがVision-Sという電気自動車のコンセプトモデルを展示しましたが、吉田社長によると、自動車産業との関わりを増やしていきたいという意図もありつつも、むしろもっと社会的な変革への対応が念頭にあっての戦略だといいます。
エレクトロニクス業界は、過去10年以上に渡って「モバイルによる社会変革」が続いてきました。すべてはモバイル端末へと価値が遷移していき、社会システムも大きく変化してきましたが、そんな大変革の時代も終わりを告げようとしています。
では次なる変革のキーワードは何なのでしょうか? それこそが「モビリティ」だと考えている業界リーダーは多くいます。
モビリティの変化は街の形を変え、人の動きはもちろん、物流も働き方も変化します。モビリティ時代にソニーがどのように「貢献できるのか」を探る狙いがあって、自社でコンセプトカーを開発しようとしたのです。
実際にVision-Sを開発し、もっとも大きな学びになったのは、商品価値を構成する要素がソフトとハードで逆転することだったそうです。
自動車は複雑なハードウェアと小さな分散ソフトウェアの組み合わせでできているため、部品サプライヤーの力や支配力が強く、またサプライヤーをまとめ上げる大メーカーの販売力・資本力がものをいいます。
一方、EV化された自動車は大きな処理能力を持つプロセッサで制御する複雑なOS、ミドルウェア、アプリケーションが商品価値を決めるようになる一方、ハードウェアはシンプルとなり、部品点数も家電に近くなっていきます。ならば、その構造変化の中で勝負できる形があるかもしれない…というのが、吉田社長の見立てでした。
この示唆に対して「自分たちならばこういう形で貢献できるかもしれない」という気付きを得ている方もいるのではないでしょうか。ライドシェアや物流、タクシー配車、宿泊、旅行手配、電力グリッドなどとの接続を担うミドルウェアという手もあろうし、それらをモバイルの世界とブリッジすることを考えてもいいかもしれません。
モビリティによる社会変革を想像する先に、どんな新しい価値が生まれるか。新しい領域だけに、そこには大きな可能性という余白があるのです。
テクノロジーで
変化する街作り
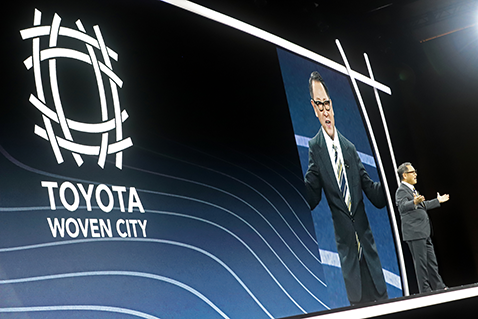
モバイル時代の社会変革も様々な粒度で起きてきましたが、モビリティ時代の社会変革はさらに幅広い粒度で拡がっていくと予想されます。
すでに中国では自動運転技術を前提として、住空間と人が行き交う階層、物流階層などを分離した都市計画が実行に移されていますが、トヨタは2018年に発表していた東富士工場跡に建設するスマートシティ「TOYOTA WOVEN CITY」を発表しました。
詳細は発表時の動画を参照いただきたいのですが、自動運転や自動配送技術を使った多階層の都市計画は、中国政府あるいはグーグルが構想するものにも通じています。
トヨタはまず、自社社員が住む街として、そこでデータを収集。より快適な街作りへとつなげていく計画のようです。
トヨタの作った映像で想像できるように、未来の街はその形が従来とは大きく変わる可能性があります。街の形が変われば人の動線は変化し、人の動線が変化すれば変化する事業もたくさん生まれるでしょう。
モバイルの時代には位置情報や決済機能などを用い、シェリングエコノミーが発展しましたが、街全体が変化するなら、もっと広範囲の影響が出るでしょう。
トヨタが街作りから始めるのも、まずは作ってみなければ、新しい価値を生み出すアイデアが生まれないからではないでしょうか。
5Gサービスが日本でも始まり、モビリティ時代はこれから幕を開けます。
2020年、すべての企業に、新しい時代に向けた事業参画のチャンスは開かれているのです。
大阪万博で見え始める
「空飛ぶタクシー」の現実味

最後に、やはりCESで注目を集めているジャンル「エアモビリティ」を紹介しましょう。エアモビリティとは、いわゆる「空飛ぶクルマ」というジャンルで、日本でも経産省の肝いりで日本発ベンチャーのCartivatoが発表した「Sky Drive」も話題となっています。
観光スポットのタクシーやレンタルカー会社に「空飛ぶ車」を提供し、空の時間を提供する(時間貸しで使用する)サービスや、ウェアラブルカメラの搭載で社内の風景(映像)を記録(編集)。こうすることで、乗った後も楽しめる工夫をして、旅の思い出づくりをサポートする機能をまとめ、エンターテインメントとして空飛ぶ車「Sky Drive」をパッケージ化しようとしているのです。
「空飛ぶ」というと荒唐無稽に思えますが、その要素技術はドローン技術に基づきます。自動運転、自動管制技術を組み合わせて、サイズを大きくしていけば、人が乗れるクルマになるのは自明でしょう。
このアイデアには、もちろん多数の競合が登場しています。
CESでもベルヘリコプター社や、韓国ヒュンダイ自動車が、米ウーバーテクノロジーズと提携した空飛ぶタクシーを発表しました。タクシーとは言うものの、その実態は垂直離着陸が可能な航空機の一種。電動で動作するため電動垂直離着陸(eVTOL)機と呼ばれています。
ヒュンダイが開発しているのは「S-A1」と呼ばれるもので、8つのローターを搭載して4人を運ぶことが可能です。それ自身は「巨大なドローン」であり、ヘリポートのようなスペースがあれば運用できるといいます。
経産省はエアモビリティというジャンルを育てるため、トヨタ、ダイハツ、NEC、パナソニック、日本航空、全日空、ヤマトホールディングスなどと社会的な枠組みも含めた取り組みをしています。東京オリンピックで初披露を…という声があり、何らかの形で披露される可能性はありますが、今のところ現実的な目標とされているのが2025年大阪万博です。
経産省が積極的に進めようとしているのは、水素燃料を用いたエアモビリティ技術。水素ステーションを持つ「ポート」を設置し、万博の時期には大阪と東京で実際にエアモビリティを用いた移動サービスとして提供する計画です。
東京でも河川沿いをルートとする航路を設定し、タクシー型サービスを提供する計画がすでに具体的な形で提案されているといいます。技術的にはこなれている分野だけに、制約は動力源と、動力源ごとの航続距離などの問題、それに法規制や安全性確保などに集約されるでしょう。
「空飛ぶクルマ」「空飛ぶタクシー」。これらの言葉は極めて未来的に語られてきましたが、いよいよリアリティのあるものになってきたといえるでしょう。

本田 雅一(ほんだ まさかず)
フリージャーナリスト・コラムニスト
テクノロジジャーナリスト、オーディオ&ビジュアル評論家、商品企画・開発コンサルタント。
技術を起点に経済的、社会的に変化していく様子に着目し、書籍、トレンドレポート、評論、コラムなどを執筆。
![[第17回]デジタル庁の成功を全力で応援すべき理由](img/thumb_vol17.jpg) [第17回]
[第17回]
デジタル庁の成功を全力で応援すべき理由![[第16回]「ゲーム機高額転売」問題から読み取る、新しい事業開発の可能性](img/thumb_vol16.jpg) [第16回]
[第16回]
「ゲーム機高額転売」問題から読み取る、新しい事業開発の可能性![[第15回]インテル独占状態のCPU市場に異変。アップルが全面採用した「Arm」](img/thumb_vol15.jpg) [第15回]
[第15回]
インテル独占状態のCPU市場に異変。アップルが全面採用した「Arm」![[第14回]急成長するアプリ経済圏から透かしてみる日本市場](img/thumb_vol14.jpg) [第14回]
[第14回]
急成長するアプリ経済圏から透かしてみる日本市場![[第13回]テレワーク需要増加で変わる仕事環境。業務環境改善の機会に](img/thumb_vol13.jpg) [第13回]
[第13回]
テレワーク需要増加で変わる仕事環境。業務環境改善の機会に![[第12回]モバイルからモビリティへ。テクノロジーによる社会変革の軸が変化](img/thumb_vol12.jpg) [第12回]
[第12回]
モバイルからモビリティへ。テクノロジーによる社会変革の軸が変化![[第11回]ウェアラブル機器の応用で拡がる「地域医療」](img/thumb_vol11.jpg) [第11回]
[第11回]
ウェアラブル機器の応用で拡がる「地域医療」![[第10回]身近にある「情報格差」。世代による「情報への接触方法」の違いとは?](img/thumb_vol10.jpg) [第10回]
[第10回]
身近にある「情報格差」。世代による「情報への接触方法」の違いとは?![[第9回]声優ラップ「ヒプノシスマイク」の新しい共創マーケティング](img/thumb_vol09.jpg) [第9回]
[第9回]
声優ラップ「ヒプノシスマイク」の新しい共創マーケティング![[第8回]プレサービスが開始された5G。本当の主役は中堅企業](img/thumb_vol08.jpg) [第8回]
[第8回]
プレサービスが開始された5G。本当の主役は中堅企業![[第7回]共感をキーワードにした新たなファッションECとは?](img/thumb_vol07.jpg) [第7回]
[第7回]
共感をキーワードにした新たなファッションECとは?![[第6回]「米国のファーウェイ制裁」が及ぼす影響は決して小さくない](img/thumb_vol06.jpg) [第6回]
[第6回]
「米国のファーウェイ制裁」が及ぼす影響は決して小さくない![[第5回]「社員同士で報酬を贈りあう。お礼の原資は会社負担」ユニポスが見せた意外な効用](img/thumb_vol05.jpg) [第5回]
[第5回]
「社員同士で報酬を贈りあう。お礼の原資は会社負担」ユニポスが見せた意外な効用 [第4回]
[第4回]
「リーボック」復活にみるマーケティングトレンドの変化![[第3回]その情報、どう扱われているか、ご存じですか?](img/thumb_vol03.jpg) [第3回]
[第3回]
その情報、どう扱われているか、ご存じですか?![[第2回]日本人が知っておくべき中国の電気自動車事情](img/thumb_vol02.jpg) [第2回]
[第2回]
日本人が知っておくべき中国の電気自動車事情![[第1回]いまさら聞けない「5Gで何が変わる?」](img/thumb_vol01.jpg) [第1回]
[第1回]
いまさら聞けない「5Gで何が変わる?」

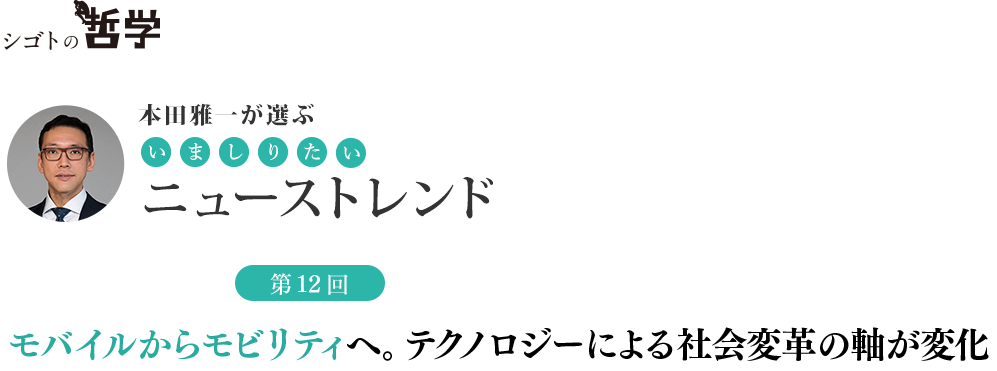
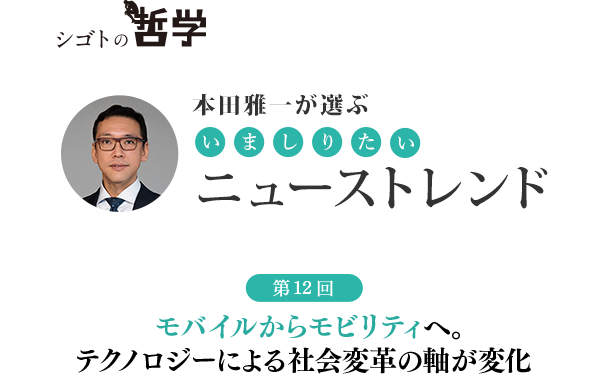
![[Vol.4] ローカル鉄道を楽しもう](../img/img_preference_vol93.jpg)
![[Vol.1] 小学生の文房具](../img/img_innovation_vol80.jpg)

![[Vol.88]特別対談「人を活かす」栗山英樹さん(北海道日本ハム…](../img/img_feature_vol88.jpg)