2020年、テクノロジー業界には大きな波がやってこようとしています。それは移動体通信網、いわゆる携帯電話ネットワークが第5世代へと突入していくこと。ただし、いきなり2020年に世の中が大きく変化するわけではありません。
3G、あるいは4G(LTE)世代では、急速に端末市場が立ち上がり、一気に広がっていくこととなりました。しかし、5Gではすべての特徴が最初から利用できるわけではなく、IoT時代を切り開くといわれている「大容量(より多くの機器が接続できること)」が実現されるのは、まだしばらく先となることでしょう。
一方で現在、もっとも応用分野としては大きなスマートフォンの活用は、実は5Gになっても新しい用途開拓が難しい状況といえます。より良いスマートフォンにはなっても、イノベーションを引き起こす力があるかといえば、疑念を抱かざるを得ません。実は端末の進化については、期待されるほど見通しが明るくはないのです。
これはすでに5G端末が発売されている諸外国でもいえることで、端末はより高速なスマートフォンにしかなっていないのが現状です。
そこで注目されているのが、各業界の規制緩和です。様々な規制において書かれている「手法」を取り払い「目的」に書き換えることで、テクノロジーによるイノベーションを引き起こそうとしています。
5Gを前提とした規制改革の
洗い出しが進行中

法律による規制は、その法がつくられたときには必要なものであっても、時代が変化してしまうと陳腐化する場合が多くあります。
たとえば極めて身近なところでいえば、公共料金の決済は紙の伝票で行わねばなりません。もはやネットの時代だというのにです。お役所だけの問題でしたら、まだそれでも民間への影響は少ないものです。しかし、コンビニ決済が一般的といえる現在、公共料金の伝票を紙で処理することによるロスはコンビニ業界で問題になってきています。
上記は笑い話に近いものですが、同様のことは5Gでイノベーションが期待される非常に幅広いジャンルで存在します。今年6月に政府は規制改革会議を立ち上げ、来年夏までに「どのような規制がイノベーションを妨げるか」、各業界からの意見を集めて洗い出し、2021年夏までに法改正の提案を行っていくと決めました。
たとえば、化学プラントは1年に1度、1日操業を止めて人間が目視で設備の点検を行わねばなりません。しかし、多数のセンサーや高精細カメラを配置し、秒単位でAIが異常診断や調整を繰り返す方が、当然ながら安全性は高まります。
もちろん、以前ならばプラントを止め、目視確認が必要だったことはいうまでもありません。しかし特定エリアを5Gの傘においてネットワーク化した方が、コストも効率も良くなることは自明といえるでしょう。
まだ具体的な洗い出しが行われていませんが、ネットワークを活用した遠隔医療だけではなく、お年寄りの見守りや介護に関しても、5GネットワークとIoT、あるいはウェアラブルデバイスの活用が望まれているのです。
一方で活用のためには、バイタル情報などをどのように扱うかといったプライバシーに関するポリシーも策定が必要になってくるはずです。
5G前に進む
ウェアラブルデバイスの活用

規制改革で一気に物事が進むかどうか疑問を持つかもしれませんが、医療と健康、あるいは見守りといった領域に関しては、想定通りに進むのではないかと期待をしています。理由は、すでに現行のデバイスやネットワークでプラクティスが積まれているからです。
たとえば慶應義塾大学病院で、数年前から循環器内科で不整脈先端治療を研究している木村雄弘特任講師は、約4年前にApple Watchから得られる情報を医療分野に活用する研究を行っていました。
現在はこの知見を生かし、Apple Watchの情報を活用した医療を赤坂の「小川聡クリニック」で活用。治療や予防医療などに活用しているのです。もはや、ウェアラブルデバイスを用いた医療は、大学病院を飛び出て地域医療へと広がりを見せているのです。
筆者はアップルCEOのティム・クック氏が木村医師を訪ねたとき、両者の話を伺う機会がありました。
木村医師は「手術後の患者さんや、不整脈を持つ患者さんにApple Watchを着けてもらうことで、素早い診断と治療へと結びつけたり、生活習慣改善の指導を明瞭に行えるようになった」と話していました。
さらに木村医師は「Apple Watchは端末内で情報を暗号化し、手元のiPadに情報が届くようになっているためプライバシー保護の点でも好ましい。安心して医療研究や診察に使える」と使用感を述べていたのです。
規制改革でセンサーやデバイスを
使った地域医療が前進

この取材の中で、クック氏は「日本でもECG(心電図)計測機能が使えるよう調整している」と話していました。不整脈には多くの種類があり、診断には心電図が不可欠ですが、発作は不定期にしか起きません。ECGを計測できるデバイスを携帯できれば、検査を経ずともダイレクトに治療に入ることが可能なはずです。
しかし、Apple Watchだけではなく、ウェアラブルデバイスを用いたECG計測機能は厚生労働省ではまだ認可されていません。これも規制改革が必要なひとつの例です。既に米国ではさらに踏み込んで、エンドユーザーが自分のデバイスを用いて臨床試験に参加できる枠組みがあります。
来夏までかかるという規制改革で、医療分野を5G時代に沿ったものにすることでの変化は極めて多いでしょう。ウェアラブルデバイスだけでも、地域医療は劇的に変化していきます。さらに、あらゆる要素がセンサーで結ばれ、それをリアルタイムに監視できるようになれば、超高齢社会の中で、地域医療の新しい扉を開き、時代は大きく変わっていくに違いありません。

本田 雅一(ほんだ まさかず)
フリージャーナリスト・コラムニスト
テクノロジジャーナリスト、オーディオ&ビジュアル評論家、商品企画・開発コンサルタント。
技術を起点に経済的、社会的に変化していく様子に着目し、書籍、トレンドレポート、評論、コラムなどを執筆。
![[第17回]デジタル庁の成功を全力で応援すべき理由](img/thumb_vol17.jpg) [第17回]
[第17回]
デジタル庁の成功を全力で応援すべき理由![[第16回]「ゲーム機高額転売」問題から読み取る、新しい事業開発の可能性](img/thumb_vol16.jpg) [第16回]
[第16回]
「ゲーム機高額転売」問題から読み取る、新しい事業開発の可能性![[第15回]インテル独占状態のCPU市場に異変。アップルが全面採用した「Arm」](img/thumb_vol15.jpg) [第15回]
[第15回]
インテル独占状態のCPU市場に異変。アップルが全面採用した「Arm」![[第14回]急成長するアプリ経済圏から透かしてみる日本市場](img/thumb_vol14.jpg) [第14回]
[第14回]
急成長するアプリ経済圏から透かしてみる日本市場![[第13回]テレワーク需要増加で変わる仕事環境。業務環境改善の機会に](img/thumb_vol13.jpg) [第13回]
[第13回]
テレワーク需要増加で変わる仕事環境。業務環境改善の機会に![[第12回]モバイルからモビリティへ。テクノロジーによる社会変革の軸が変化](img/thumb_vol12.jpg) [第12回]
[第12回]
モバイルからモビリティへ。テクノロジーによる社会変革の軸が変化![[第11回]ウェアラブル機器の応用で拡がる「地域医療」](img/thumb_vol11.jpg) [第11回]
[第11回]
ウェアラブル機器の応用で拡がる「地域医療」![[第10回]身近にある「情報格差」。世代による「情報への接触方法」の違いとは?](img/thumb_vol10.jpg) [第10回]
[第10回]
身近にある「情報格差」。世代による「情報への接触方法」の違いとは?![[第9回]声優ラップ「ヒプノシスマイク」の新しい共創マーケティング](img/thumb_vol09.jpg) [第9回]
[第9回]
声優ラップ「ヒプノシスマイク」の新しい共創マーケティング![[第8回]プレサービスが開始された5G。本当の主役は中堅企業](img/thumb_vol08.jpg) [第8回]
[第8回]
プレサービスが開始された5G。本当の主役は中堅企業![[第7回]共感をキーワードにした新たなファッションECとは?](img/thumb_vol07.jpg) [第7回]
[第7回]
共感をキーワードにした新たなファッションECとは?![[第6回]「米国のファーウェイ制裁」が及ぼす影響は決して小さくない](img/thumb_vol06.jpg) [第6回]
[第6回]
「米国のファーウェイ制裁」が及ぼす影響は決して小さくない![[第5回]「社員同士で報酬を贈りあう。お礼の原資は会社負担」ユニポスが見せた意外な効用](img/thumb_vol05.jpg) [第5回]
[第5回]
「社員同士で報酬を贈りあう。お礼の原資は会社負担」ユニポスが見せた意外な効用 [第4回]
[第4回]
「リーボック」復活にみるマーケティングトレンドの変化![[第3回]その情報、どう扱われているか、ご存じですか?](img/thumb_vol03.jpg) [第3回]
[第3回]
その情報、どう扱われているか、ご存じですか?![[第2回]日本人が知っておくべき中国の電気自動車事情](img/thumb_vol02.jpg) [第2回]
[第2回]
日本人が知っておくべき中国の電気自動車事情![[第1回]いまさら聞けない「5Gで何が変わる?」](img/thumb_vol01.jpg) [第1回]
[第1回]
いまさら聞けない「5Gで何が変わる?」


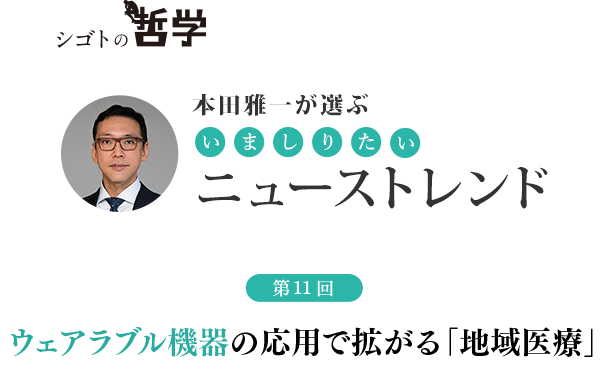
![[Vol.3] 雑誌の付録](../img/img_innovation_vol82.jpg)



![[Vol.9] 2020年の先を見たサイバーセキュリティ対策](../img/img_it_vol89.jpg)

