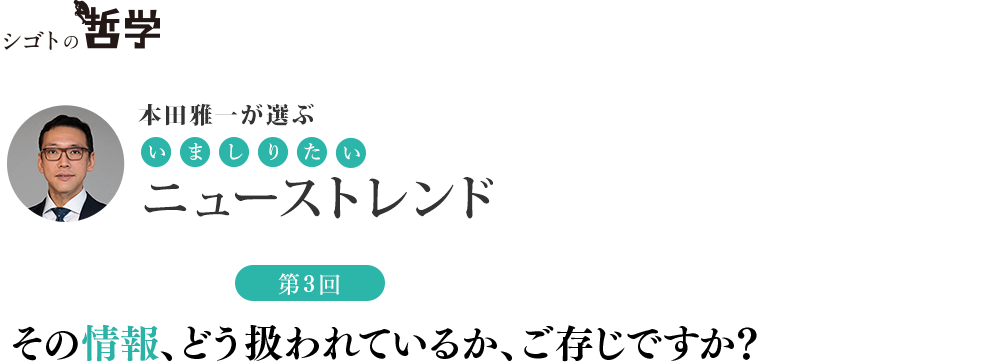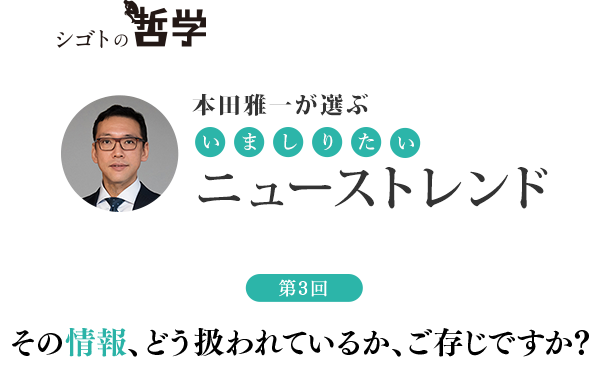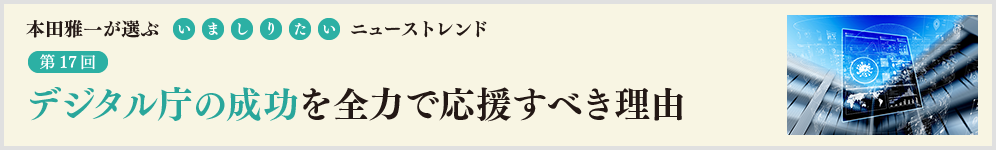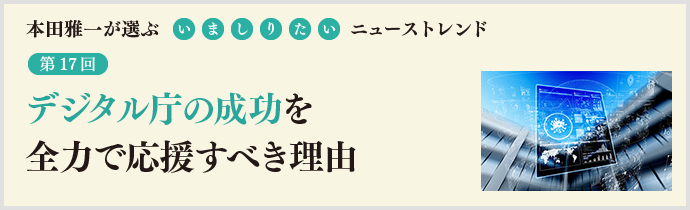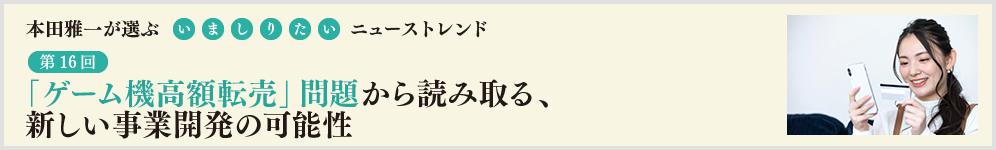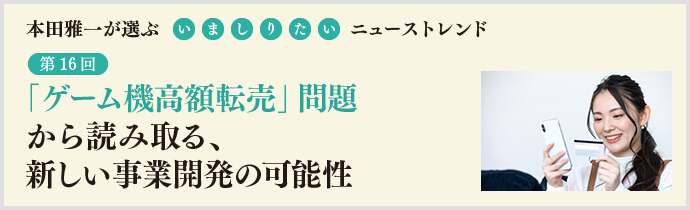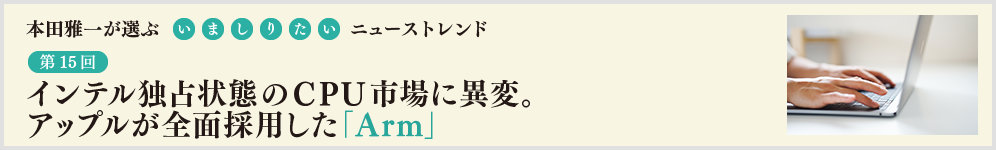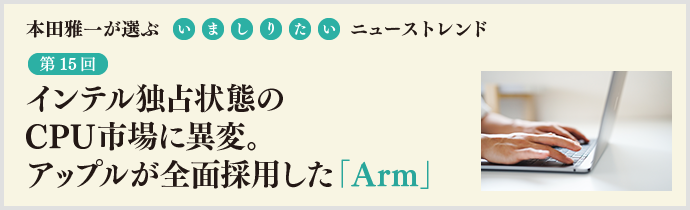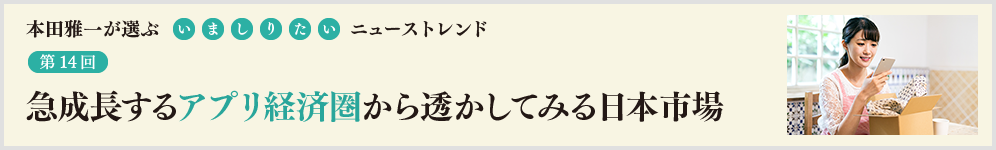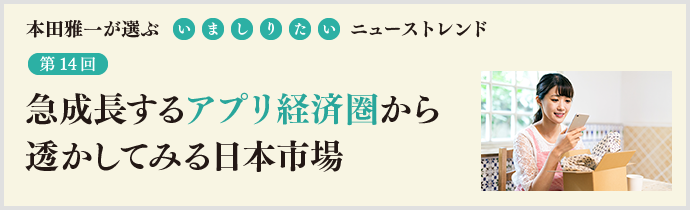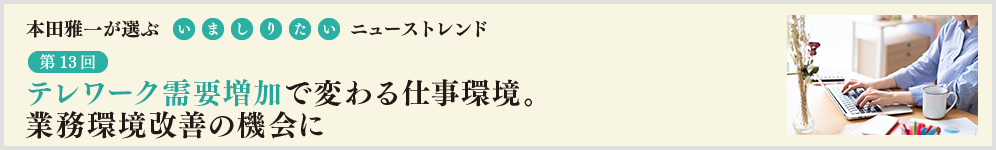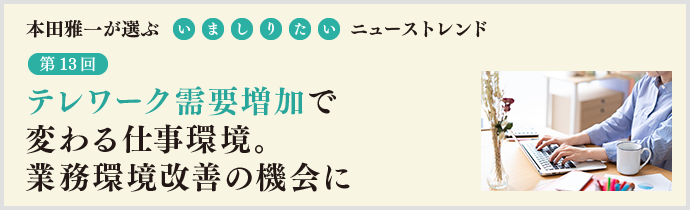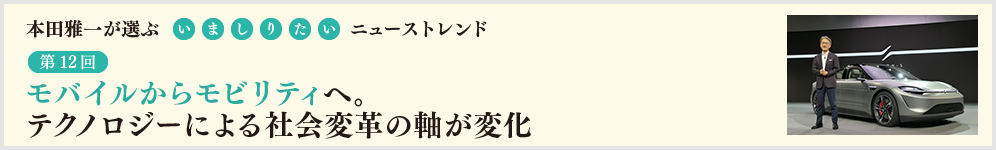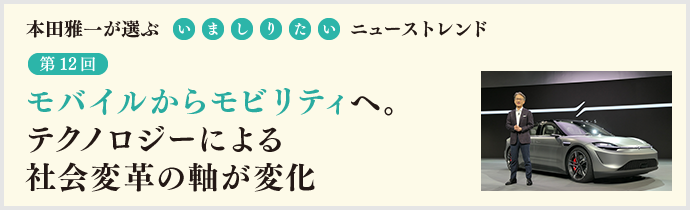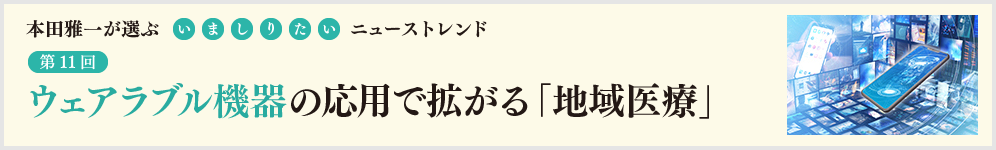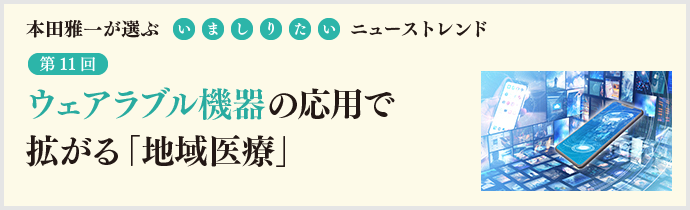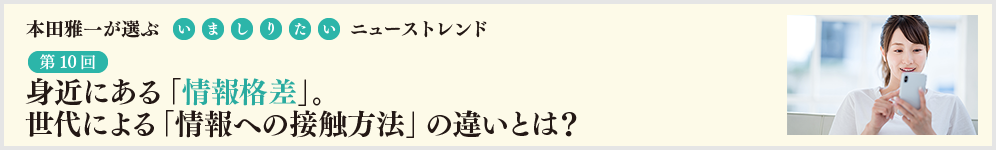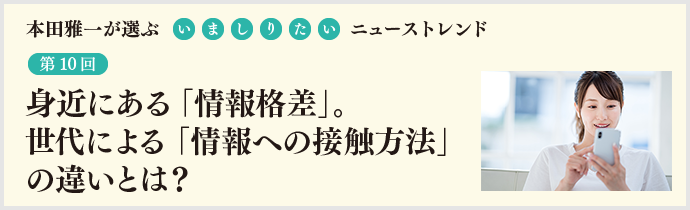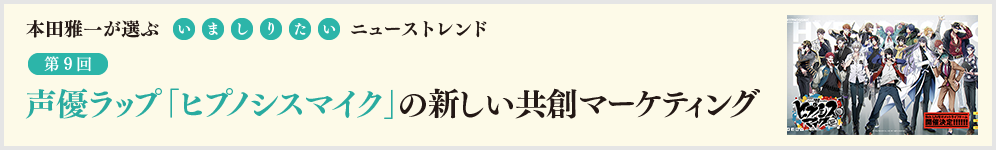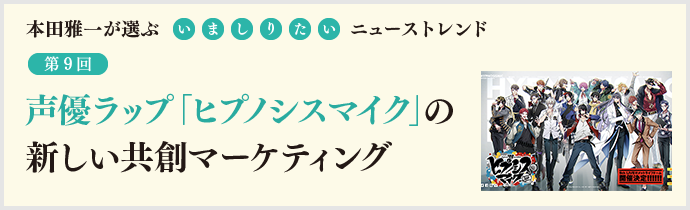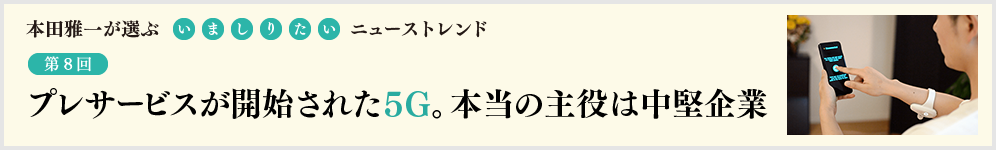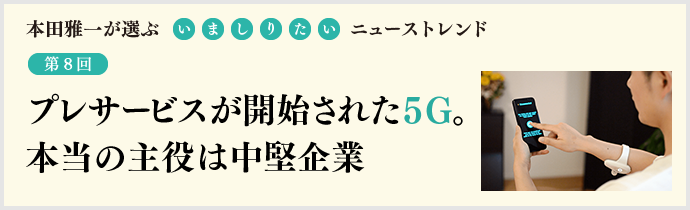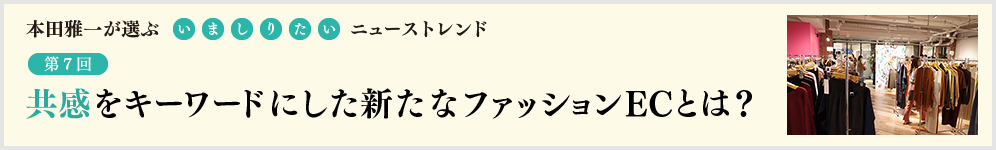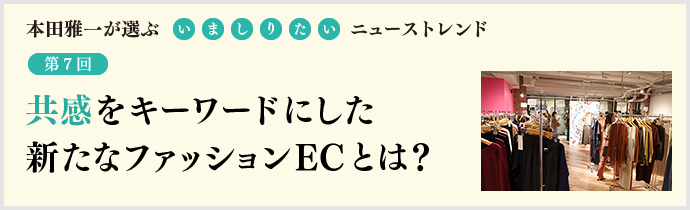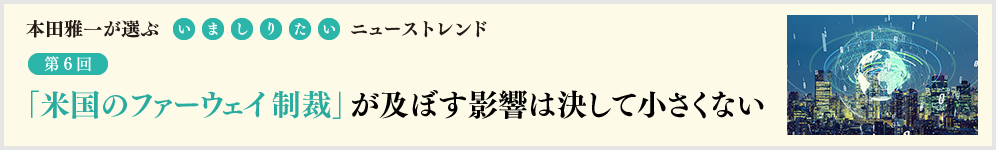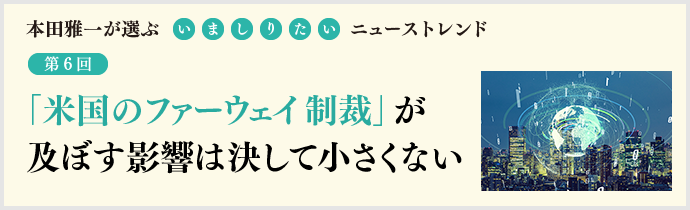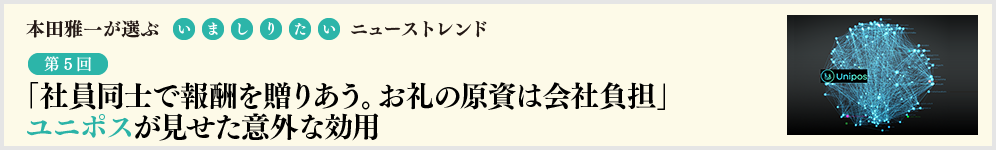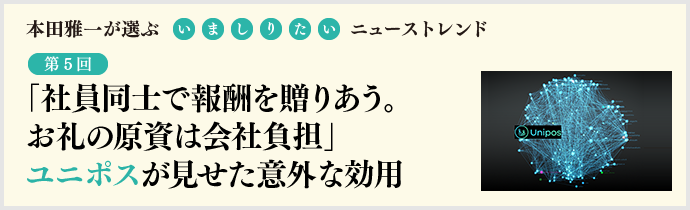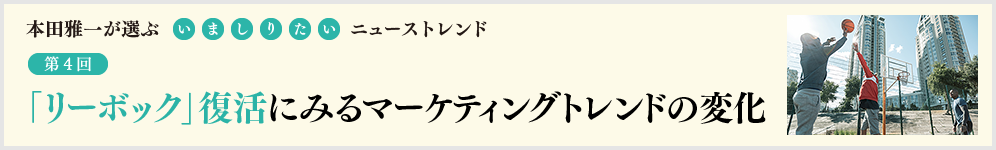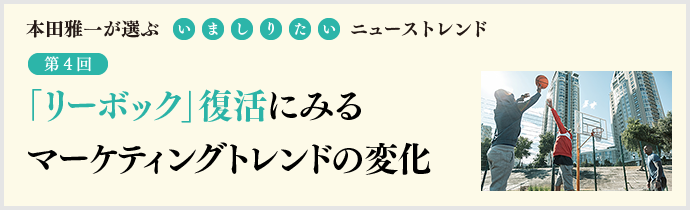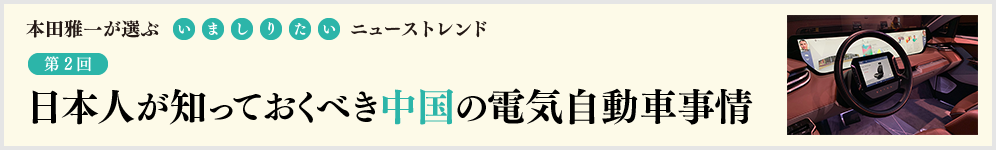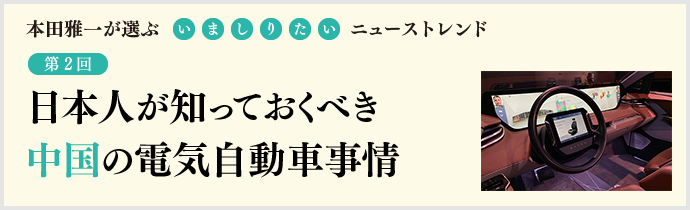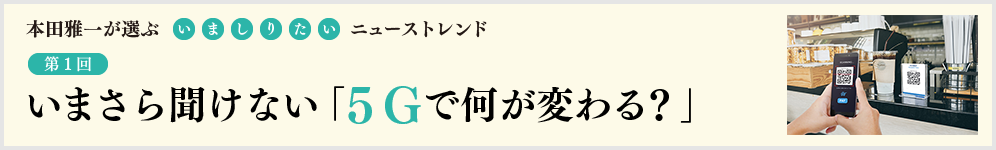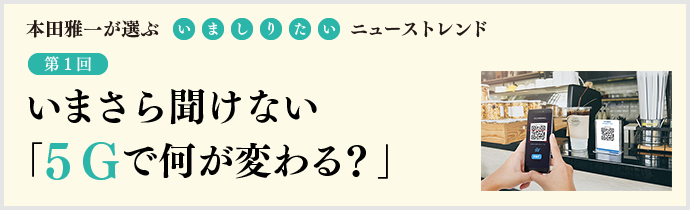利用者のウェブ、アプリ上の行動履歴や個人情報などのデータを収集・分析することで、さまざまな「傾向」を探る、いわゆる「データマイニング」というジャンルは、過去10年ほどで一般的なマーケティングや広告にも応用されるようになってきました。背景には社会全体の情報化が進み、人々の行動について統計情報を取りやすくなっていることがあります。また、個人の行動履歴という面から見ると、スマートフォンの普及によって、個人レベルでも「暮らし」と「ネットワークサービス」が結びつくようになってきたことが大きいのだと思います。
データ解析による、さまざまな「最適化」は社会の効率を高めたり、サービスや製品の機能を一段と心地よいものにしたりしますが、一方で行動履歴などのデータを広告に使われることを嫌うひとたちもいます。また海外では、データを解析することで、所得層や子どもたちの学力偏差値を地域ごとに分類したマップを不動産取引に応用している例もあり、データ収集と分析について一定のルールやモラルを求める声も大きくなってきました。
そんな中、iPhoneを開発・販売しているアップルは、このところ「私たちは個人データの収集や解析とは無関係だ」と繰り返し訴求するようになりました。同社は自社のハードウエア製品に対しては饒舌(じょうぜつ)ですが、それ以外、例えば他社の利害に関係するようなことには、可能な限り「意見を発信しない」とされる会社です。
そんなアップルがこうしたメッセージを発信する背景には何があるのでしょうか?
「データを持つ」ことの
優位性とリスク

個人データの扱いに関して注目が集まっている理由はたくさんありますが、ここ数年、特に話題になりがちな理由は、大きく分けると3つあります。
1つは2018年5月に欧州でGDPR(EU一般データ保護規則)が施行されたことです。この規則では、EU域外の企業がEU域内で集めた個人情報を無断で持ちだすことを禁じています。その目的や弊害などにはさまざまな議論がありますが、膨大になるのでここでは、「GDPRの施行で多くの企業がデータ活用戦略の変更やデータの扱いに関する規則の見直しを行った」とだけ書いておきます。
次に、デジタルマーケティングにおいて、個人情報解析を基礎にしたPDCAサイクルの活用が進んできたことが指摘できます。PDCAとは「Plan=計画」「Do=実行」「Check=評価」「Action=改善」で、仕事の能率改善を目的としてワークフロー全体を見直す際などに使われることが多い言葉です。
昨今話題になっているのは、このPDCAサイクルのリスティング広告(ターゲティング広告)やデジタルマーケティングへの応用です。これは、スマートフォン上でのアプリ利用やウェブ上での振る舞いなど、さまざまな行動履歴を評価し、目的(計画)に応じて実施するマーケティング施策にフィードバックするもの。また、その結果を再評価してプランを修正することで、広告や物販の数字を上げるデジタルマーケティング手法として注目されています。
ただし、効果的であるがゆえに、データの収集方法に対して透明性を求める声が強いことも確かです。例えば、グーグルはほとんどの収入を広告に依存していますが、彼らの売りはPCやスマートフォンの利用者から集まるサービスを利用した履歴データです。またフェイスブックは詳細な個人データを保有することを強みに、同様のリスティング広告やクーポン発行などの事業を効率的に行って売り上げを伸ばしてきました。
もっともそれが悪というわけではありません。リスティング広告は「A」という商品を欲しがっている顧客に「A'」という商品を告知する手法ともいえますが、一方で受け手にとって必要な情報を提供するためにデータを応用しているという見方もできます。しかしデジタルマーケティングとは無関係の企業にとってみれば、データを持つことはリスクでしかありません。万が一、分析のために収集している個人データが外部に流出すれば大きな問題になりますし、自社製品やサービスの改良に個人情報を利用している……といった見方をされると、あまり印象のいいものではありません。
最後に、個人データの扱いに注目が集まっている3つ目の理由は、個人データの分析結果が、さまざまな形で「悪用されている」と明らかになってきていることです。先述した地域ごとに学童の学力や収入レベルを分類したマップは、不動産取引時の参考にされているそうです。良識のある企業なら、もちろんそんなことはしませんから、広告収入を最大化したり、売り上げを高めるために何らかのデータが必要だったりといったマネタイズ要因がない限り、データは「持っていない方がリスクが低い」と言えるでしょう。
「行動履歴の匿名性」を
担保しても
機能性は失われない

アップルがこのところ、データプライバシーについて強い発言を繰り返しているのも、そうした観点――すなわち、個人データを保有することそのものが事業リスクであるとの判断があるからでしょう。ネット社会における新しい支配者として、グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップルをまとめて「GAFA」と表現したりしますが、この中で「データ解析が収益に直結しない」企業は、実はアップルだけです。
グーグルとフェイスブックは広告が主な事業ですし、アマゾンは物販を最大化するためにデータを最大限に活用しています。アップルだけが、ほとんどの収益をハードウエアの売り上げから得ているため、プライベートな情報を集めたからといって売り上げが大きく伸びるわけではありません。
むしろ、個人情報を大切にする――すなわち「個人情報は集めない」という方針を打ち出した方がブランド力を強化できますし、顧客の安心感も引き出せます。個人情報の流出がニュースになることが多い昨今、「データを持つ」ことは「評判を落とすリスク」を高めることと同義になるという考え方です。
前述したGDPRが施行されたのは昨年(2018年)ですが、内容が決められたのは2016年のこと。基本的な基準は、さらにその2年前から提唱されていましたが、アップルはその時点でテック企業では唯一、GDPRの新しい規則に対応していました。というのも、創業者であるスティーブ・ジョブズ氏の方針で「顧客の情報を扱う以上、顧客がコンピュータを扱う際、アップルはその情報を保存したり、追跡したりしない」というルールを作ったからです。
例えば、スケジュールを参照しながら「何時に出発して、どの経路で移動すると、何時ぐらいに到着しますよ。目的地と予定の内容はこうです」といったアドバイスをスマートフォンのアシスタント機能から受けたことがある人も多いでしょう。こうした機能を使う際、iPhoneは端末内のスケジュールをチェックし、クラウドに問い合わせて経路などを確認します。現在位置や目的地、到着時間、いつも使っている交通手段などがわからなければ、こうしたアドバイスは行えません。
しかしiPhoneは端末とは無関係の固有IDを生成し、さらにそれを3分に1回変更してしまうため、サービス事業者側は「どの端末からの問い合わせ」なのかを特定することができません。普段使っている交通手段の学習も、端末内で保存・管理されますから、サービス事業者は特定の個人、あるいは匿名としてすら個人の行動のパターンを把握できません。
アップルは「スマートフォンに集まるすべての情報を収集しなくても、クラウド型サービスを元に便利な機能は提供できる」と主張し、自分たちは他の比較されている会社とは違うことをしているのだ、とアピールしているわけです。
不要な情報は
持たないことで
リスク回避

そうはいっても、世の中の多くのサービスがデータ取得による高精度なリスティング広告によって低価格、あるいは無料で提供されていることは間違いありません。フェイスブックに代表されるSNS、あるいはグーグルの各種サービスがいきなり有料になることをほとんどの人は望んでいないでしょう。
実際、個人データによって広告市場を活性化させることについて、問題視する意見は少数派です。アップルも「自分たちは関係ない。私たちはハードウエアメーカーなのだから」と表明しているだけで、広告事業を悪く言っているわけではないのです。
では何が問題なのでしょうか? GDPRの精神は「自分たちの行動について分析され、日常生活や消費活動、あるいは企業活動に影響を与えられるなら、その全体像を把握できるべきであり、把握できた上で許可すべきである」ということに尽きます。データを提供する際に「許可しますか?」というボタンが現れたり、契約書で許可を求めたりはもちろんですが、「どのような情報を集め、どのように使われるのか」を、難しい文書だけでなく、全体像が把握できるようなツールを提供して伝える必要があります。
こうした個人データの収集については、テレビ広告などのような規制官庁もなければ、監視する仕組みもまだ不十分だからです。一方で、もし事業を進める上で、あるいは何らかの機能やサービスを提供する上で、必要がない情報であれば、可能な限り切り離し、捨ててしまい、また必要な情報も匿名化していくのが賢明でしょう。
「不要な情報は持たない」
これは、情報システムにおけるリスクを考える上で、個人情報に限らず、あらゆる情報についていえることかもしれません。

本田 雅一(ほんだ まさかず)
フリージャーナリスト・コラムニスト
テクノロジジャーナリスト、オーディオ&ビジュアル評論家、商品企画・開発コンサルタント。
技術を起点に経済的、社会的に変化していく様子に着目し、書籍、トレンドレポート、評論、コラムなどを執筆。