自民党総裁に就任した菅首相は、日本政府全体をデジタル化するための「デジタル庁」を、2020年内にも設置するための準備委員会を設立しました。
デジタル庁は首相直轄の部門となり、各省庁に対して横断的に政府のデジタル化を進める司令塔役になると報道されています。
これまで、省庁ごとにシステム部門があり、それぞれのITシステムは個別に開発、管理などがされていました。しかし個々の現場だけに収斂させたシステムは、相互の接続性が低いものです。従来からあった仕事のやり方を情報システムにしているためで、いざ大規模な施策が必要となった際、情報の流れが目詰まりし、迅速な対応が取れない場合があります。国民一人当たり10万円の給付金を振込む際、地方自治体が口座確認に手間取った例などはその典型例と言えるでしょう。この際、マイナンバーカードの普及が進んでいないことも、各種手続きの遅れや手続きにかかるコストの高さなどの弊害を浮き彫りにしました。
コロナ禍で政府のデジタル化ニーズが可視化されてきた現在こそ、全力でこの取り組みを支援すべきではないでしょうか。
行政機関を
デジタルトランスフォーメーション

新しい組織の立ち上げであるため、話題は組織編成や予算、権限といった部分に目が行きがちで、報道に関しても現時点では「省庁をまたぐ横断的な組織をどのように位置付けていくか?」といった論調のものが多くなっています。
しかし、俯瞰してこの取り組みを見るならば、デジタル庁の役割は「日本の行政機関をデジタルトランスフォーメーションする」ことと言えます。
デジタルトランスフォーメーションは「DX」とも略され、さまざまな企業が取り入れ成功してきているものです。DX事例は近年数多く紹介されているため、ITについて詳しくないという読者でも、その名前ぐらいは聞いたことがあるでしょう。
この連載で1月にラスベガスで開催された展示会「CES」をレポートした際、多くの企業がDXするための多様な展示があったことをお伝えしました。
従来のIT化とDXの違いは何かと言われれば、実は概念的な違いしかありません。双方ともコンピュータ端末やネットワークを用いて、問題解決することに変わりはないのです。大きな違いは解決手法です。既存業務を情報技術で効率化するのがITシステム構築の本質とするなら、DXは業務全体をデジタル化した上で再構築することが本質と言えます。
デジタル化以前の業務プロセスを一旦脇に置いて、組織構成や業務フロー、そこから派生する顧客向けサービス、外部協力企業との連携や内部組織の連携など、あらゆるプロセスを見直すことで業務効率を上げるだけでなく、職場環境や顧客サービスの品質も高めることが可能です。
航空業界での
大規模なDX事例が話題に

前述したCESではデルタ航空のCEOが登場し、航空業界のDX事例を紹介していました。
ここ数年で、航空業界でのネットやアプリの活用は進み、アプリを使って発着状況を確認したり、チケットの手配やアップグレード手続き、マイレージ会員情報の管理などを行えることは皆さんご存知でしょう。しかし、そうした表層部に止まらず、業務の手順や社内ルールなども含め、大胆にシステムを改良することで「当たり前を当たり前」にするために、大胆にシステムを入れ替えていることを取り上げていました。
従来ならば、属人的でプロセスが見えにくかったゲート変更、到着機材の遅れ、それに伴うさまざまな「行動すべきこと」を、業務システムとエンドユーザー向けアプリを接続し、適切に見せることで解決しているのです。
分離されていた予約系、運行系システムを見直し、情報を整理した上で、顧客向け情報システムとも接続できるようにすることで、社内各部署がみているリアルタイムの情報を統一し、さらには顧客にまで刻々と変化する状況を可視化できるよう、システム全体を見直しました。今後はDXの範囲をさらに広げ、飛行機の到着に合わせて送迎車の手配を行ったり、送迎と連動して宿泊するホテルの準備を行うといった、他社連携までを含めたワークフロー改善を進めるという話でした。
現在はコロナで移動制限が大きく、産業全体が危機に晒されている航空業界ですが、この時期を乗り越えた先にDXが完遂されていれば、立ち直りの速度を早めることができるでしょう。
より良い社会に向けて
協力する姿勢が大切

もっとも行政サービスのDX化となると、民間サービスよりもずっとハードルが高くなります。なぜなら、あらゆる利用者とのアクセスを平準化しなければならないからです。高齢者世帯も含めて均質なサービスを提供しながら、あらゆるプロセスを見直すには、システム構築前の見直し作業だけでも膨大なものになってしまいます。
しかし、より良い行政サービスの実現は多くの国民にとってもプラスとなる取り組みです。困難のハードルが下がるよう社会全体でサポートすることも重要でしょう。もっとも簡単かつ、優先的に協力すべきことはマイナンバーカードの取得です。
マイナンバーカードがどこまで行き渡るかで、行政サービスのDX化はその品質が大きく変わります。手続きに付随する個人を識別できるIDが普及すれば、新しい時代の石杖となることでしょう。
よく台湾の事例が引用されますが、日本よりも人口の多い米国の方が事例としては適切です。米国のソーシャルセキュリティ番号(SSN)は本来、年金給付のために割り付けられた番号ですが、個人を識別する番号として長年使われてきたことで、行政機関だけではなく、民間のサービスも含めて個人識別のIDとして使われています。クレジットカードはもちろん、ちょっとした会員証を作る際にもSSNを記入する欄があったりするほどなのです。プライバシーの問題もあるため、SSNと民間サービスの連動性は今後は下がっていくでしょうが、行政サービスの速度を上げていく上で、国単位、州単位、市町村単位など、どんな粒度でも活用できる共通番号としての意味は大きくなっていくことでしょう。
マイナンバーカードを取得することは、情報化、デジタル化しやすい世の中を作る上での基礎となるのです。
さまざまな粒度での
デジタル化を推進する基盤に

マイナンバーカード取得が行政サービスのデジタル化を進めるための基礎とするなら、デジタル庁が司令塔となって進める行政サービスのデジタル改革は、その後の日本社会全体の効率化を支える基盤となっていくものでしょう。
デジタル化された行政サービスの窓口、各種方法の管理、アクセスなどが安定的に提供されるようになれば、地方行政や民間企業はルールに則ることで、それぞれが必要とする情報に対して容易に接続可能になるのです。
米国SSNの例ではありませんが、国が保証するインターフェイスや情報フォーマットがあれば、それを元にあらゆる情報システムを作っていくという選択肢が取れるためです。
誰もがその長所、利点は理解できるところだと思いますが、それでも油断できないのは、日本ではDXに際して本来、必要ではない説明を求められるデジタル後進国という印象があるからです。
海外の事例の全てが日本よりも優れているとは言いませんが、米国や欧州などで取材をしている際に「DX化のために過去のシステムを見直し、あらゆるプロセスをデジタル化。顧客向けに可能な限りシンプルな窓口をアプリやウェブで用意する」といった説明が行われることは、まずありません。
なぜなら、それらはDXを実施するための大前提だからなのです。DXの本質は組織、プロセスなどの見直しにあるので、それ以前のデジタル化は議論の対象ではないのです。
しかし、「技術のことはよくわからない」と目を背けることがなければ、きっと数年後には変化を体感できるようになっているでしょう。政治的なポリシー、立ち位置などとは無関係に、優先すべきテーマとして国民全員で共有していきたいテーマではないでしょうか。

本田 雅一(ほんだ まさかず)
フリージャーナリスト・コラムニスト
テクノロジジャーナリスト、オーディオ&ビジュアル評論家、商品企画・開発コンサルタント。
技術を起点に経済的、社会的に変化していく様子に着目し、書籍、トレンドレポート、評論、コラムなどを執筆。
![[第17回]デジタル庁の成功を全力で応援すべき理由](img/thumb_vol17.jpg) [第17回]
[第17回]
デジタル庁の成功を全力で応援すべき理由![[第16回]「ゲーム機高額転売」問題から読み取る、新しい事業開発の可能性](img/thumb_vol16.jpg) [第16回]
[第16回]
「ゲーム機高額転売」問題から読み取る、新しい事業開発の可能性![[第15回]インテル独占状態のCPU市場に異変。アップルが全面採用した「Arm」](img/thumb_vol15.jpg) [第15回]
[第15回]
インテル独占状態のCPU市場に異変。アップルが全面採用した「Arm」![[第14回]急成長するアプリ経済圏から透かしてみる日本市場](img/thumb_vol14.jpg) [第14回]
[第14回]
急成長するアプリ経済圏から透かしてみる日本市場![[第13回]テレワーク需要増加で変わる仕事環境。業務環境改善の機会に](img/thumb_vol13.jpg) [第13回]
[第13回]
テレワーク需要増加で変わる仕事環境。業務環境改善の機会に![[第12回]モバイルからモビリティへ。テクノロジーによる社会変革の軸が変化](img/thumb_vol12.jpg) [第12回]
[第12回]
モバイルからモビリティへ。テクノロジーによる社会変革の軸が変化![[第11回]ウェアラブル機器の応用で拡がる「地域医療」](img/thumb_vol11.jpg) [第11回]
[第11回]
ウェアラブル機器の応用で拡がる「地域医療」![[第10回]身近にある「情報格差」。世代による「情報への接触方法」の違いとは?](img/thumb_vol10.jpg) [第10回]
[第10回]
身近にある「情報格差」。世代による「情報への接触方法」の違いとは?![[第9回]声優ラップ「ヒプノシスマイク」の新しい共創マーケティング](img/thumb_vol09.jpg) [第9回]
[第9回]
声優ラップ「ヒプノシスマイク」の新しい共創マーケティング![[第8回]プレサービスが開始された5G。本当の主役は中堅企業](img/thumb_vol08.jpg) [第8回]
[第8回]
プレサービスが開始された5G。本当の主役は中堅企業![[第7回]共感をキーワードにした新たなファッションECとは?](img/thumb_vol07.jpg) [第7回]
[第7回]
共感をキーワードにした新たなファッションECとは?![[第6回]「米国のファーウェイ制裁」が及ぼす影響は決して小さくない](img/thumb_vol06.jpg) [第6回]
[第6回]
「米国のファーウェイ制裁」が及ぼす影響は決して小さくない![[第5回]「社員同士で報酬を贈りあう。お礼の原資は会社負担」ユニポスが見せた意外な効用](img/thumb_vol05.jpg) [第5回]
[第5回]
「社員同士で報酬を贈りあう。お礼の原資は会社負担」ユニポスが見せた意外な効用 [第4回]
[第4回]
「リーボック」復活にみるマーケティングトレンドの変化![[第3回]その情報、どう扱われているか、ご存じですか?](img/thumb_vol03.jpg) [第3回]
[第3回]
その情報、どう扱われているか、ご存じですか?![[第2回]日本人が知っておくべき中国の電気自動車事情](img/thumb_vol02.jpg) [第2回]
[第2回]
日本人が知っておくべき中国の電気自動車事情![[第1回]いまさら聞けない「5Gで何が変わる?」](img/thumb_vol01.jpg) [第1回]
[第1回]
いまさら聞けない「5Gで何が変わる?」


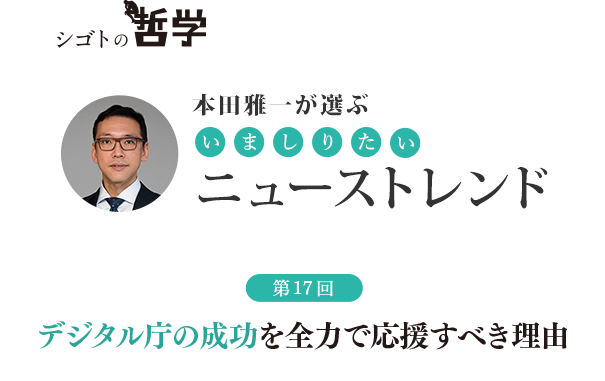


![[Vol.17]広域自然災害による被災者支援の迅速化にITはどう貢献するのか](../img/img_it_vol97.jpg)
![[42] 視覚から](../img/img_photonavi_vol97.jpg)


